
COLUMN
コラム
1級建築施工管理技士を取ると、応募できる仕事が増えるんだよな。でも難しいかな…と悩んでいるあなたへ、今日は1級建築施工管理技士になるためにはどうすれば良いかをお話します。
建築施工管理技士には、1級と2級があります。
1級建築施工管理技士の受験資格は大学の指定学科卒業後3年以上の実務経験、その他の学歴の場合は15年以上の実務経験が必要です。その他の学歴の場合の方は、2級建築施工管理技士を取得すれば、実務経験が短くなります。
そのため、まずは2級建築施工管理技士からスタートすることも近道と言えます。では、苦労して1級を取得すると2級と何が違うのでしょうか。
1級建築施工管理技士を取得後、指定講習を受講し、手続きをすると【監理技術者】となることができます。2級のままでは取得できない資格です。
監理技術者とは元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になる場合に当該工事現場に専任で配置される、施工の技術上の管理をつかさどる技術者のことです。
つまり、簡単に言うと大きな規模の工事に必要になる人、というイメージです。
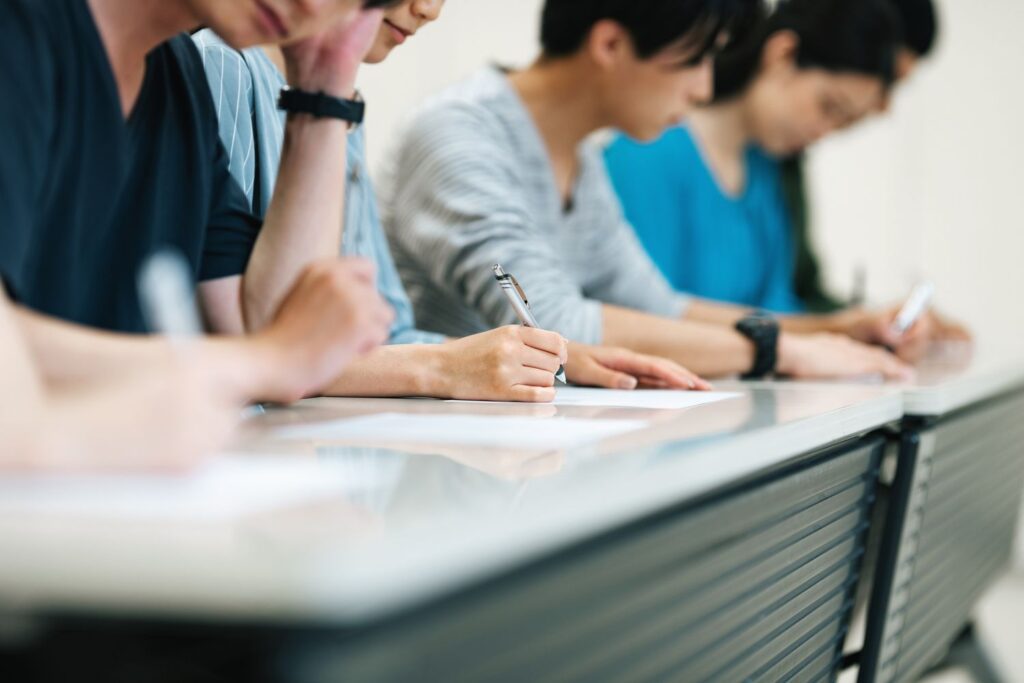
試験は2級建築施工管理技士と同様に、学科と実地の2つの試験があります。
ただし2級と異なるのは、2級では学科と実地が同時に受験可能でしたが、1級の場合は一次試験の学科に合格しなければ二次試験の実地に挑戦できないということです。
まずは学科試験の合格が必須となります。ではその試験の合格率はどうでしょう。
2級の場合は学科の合格率が35%前後、実地合格率は30%前後、1級の場合は学科の合格率が35~40%、実地の合格率が45%前後です。
2級に比べ、1級の方が難易度はあがりますが、合格率は少々上がっています。それほど皆さんが真剣に資格試験に取り組んでいるということです。

二次試験の実地試験は、実技試験ではありません。
一次試験の学科試験は選択肢から回答を選ぶマークシート形式の問題であるのに対し、実地試験は作文形式で答える筆記試験となります。
特に難しく感じるのが、自分の施工管理経験を記述する問題です。
何を書けば合格するの?とびっくりして構える必要はありませんよ。
市販されている問題集を参考に、実体験をまとめてみてください。その時のコツは、【いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように】と言われる5W1Hや、主語・述語と言った基本的な文章の作成方法に則りまとめることです。
またその文章を繰り返し書いて覚えること、誰かに読んでみてもらうことです。
自分ではわかりやすく完璧な文章だと思っても、採点者(読み手)に正しく伝わらなければなりません。
もちろん資格学校や通信教育を利用して、添削サービスを使うことなども選択肢の一つとしてあると思います。嘘や真似をして作った文章ではなく、自分の実体験を文章にまとめること、そうすれば自ずと緊張していても本番で頭が真っ白!なんてことは避けられますよ。

施工管理の仕事は、1級・2級の施工管理技士を取得していなくても携わることができます。
ですが、やっぱり資格を取得すると説得力も上がりますし、応募できる仕事も増えます。派遣の施工管理技士としても、リピーターが付いてくれる可能性も高まります。
仕事の質が高くても、資格がなければ評価が半減してしまう可能性もあります。自分の今後のためにも、ぜひ1級建築施工管理技士にチャレンジしてみませんか?
050-5482-3847
受付時間 9:00〜18:00